ろ過には物理ろ過と生物ろ過の2種類があることはご存知でしょうか?
アクアリウムをやってって名前は聞くけど・・・という方も多いと思います。
ろ過機能について研究をしていたお魚研究生が
物理ろ過と生物ろ過について解説していきます
① ろ過には「物理ろ過」と「生物ろ過」の2種類がある
② 物理ろ過は、ゴミを取るためのろ過方法
③ 生物ろ過は水質を改善するためのろ過方法

ろ過には2種類あるんだね。
そういえば、僕たちの水槽にフィルターがついていたけど
あれはどっちのろ過装置なんだろう。
物理ろ過について

概要
海水中の物理的な汚れを除去するためのろ過機構が物理ろ過です。
一般的にろ過といって想像するのは「物理ろ過」のことですね。
家庭用のアクアリウム水槽では物理ろ過と生物ろ過機能両方を兼ね備えているので2つは混合されがちですね。
物理ろ過の種類
水族館のような大型の施設では、砂濾過・膜ろか・糸巻フィルターのようなろ過設備があります。
| ろ過の種類 | 内容 |
| 砂ろ過 | 大量の水を濾過したい時は砂ろ過を用いる場合が多いです。 ろ過精度は、ろ過速度やろ過砂の厚さにもよるが、かなりの汚れを取ることができます。 泥や、プランクトン類を取りきることはできない。 |
| 水槽のフィルター | 一番よく見かけるフィルター |
| 糸巻きフィルター | 海水中の多くの微生物を取ることが出来る。糸巻によってろ過精度は大きく異なる。1μmくらいになればほとんど微生物がいなくなる。直接海水を入れるとすぐ目詰まりを起こし使い物にならなくなる。基本的には綺麗な海水を通して使う。 |
| 膜ろ過 | ほとんどいなくなる。イオン交換膜なんか使うと海水を淡水にしちゃったりする。 |
海の水を使う場合には、物理ろ過で綺麗にしたものを水槽に入れます。
ワムシなどの微生物を扱う場合や、種苗(数ミリ単位の)生産をする場合には、
よりろ過精度の高い物理ろか装置を用います。糸巻フィルターとか。
サンゴ砂、多孔質フロックとかはろ過材と、
メンテナンス
物理ろ過を行う際は、水を通常のろ過方向と逆向きに流すことで洗浄を行う「逆洗洗浄」と、ろ材を取り出して「直接洗浄」する方式があります。
ろ過の方式や、水の汚れ具合によってろ材のメンテナンス頻度が変わります。

物理ろ過だけで、こんなにたくさん種類があるんだね。
そういえばペンギンのプールにも、ろ過装置が取り付けられていたよ!
生物ろ過について

生物ろ過とは
「生物ろ過」とは微生物の働きを利用した化学的なろ過機構のことです。
魚の飼育をしていると発生する残餌(食べ残したご飯)や糞を分解してくれます。
また、魚の排泄するアンモニアを硝酸に変えてくれるという重要な働きを持ちます。
循環型の養殖設備を用いる場合はこの要素がとても大切なのです。

哺乳類は窒素を尿素にしてから体の外に出すことができるんだ。
魚の場合、毒性のアンモニアを排出してしまうから
生物ろ過は必須なんだね。

1960年代にバクテリアによる処理方法が発見されるまでは、
水槽で魚を飼うのは難しかったんだ。
魚の排泄について
魚類はおしっことしてアンモニアを排泄します。
また、水中という特殊な環境のため排泄したアンモニアがそのまま住環境に満たされてしまうのです。
1950年代くらいまでは、なんか魚が死んでしまうなーっていう状態が続いていました。硝化細菌の存在が明らかとなっていきました。哺乳類にはアンモニアを尿素に変え無毒化(まったくではないよ)する機構がありますが、魚はこの機構をもちません。
生物ろ過の種類について
「浸漬ろ床方式」「散水ろ床方式」「流動床方式」があります。
もっとも一般的なのが「浸漬ろ床方式」です。
浸漬ろ床方式・・・ろ材を海水で浸してろ過する方式。最も一般的。
散水ろ床方式・・・開放系のろ材に海水を吹きかける方式。ろ過効率が高い。
流動床方式・・・
硝化の簡単な機構について
硝化細菌(バクテリア)の働きによってアンモニアは硝酸へと酸化されます。
すごーーく簡単に書くとこんな感じです。
NH3→NO2→NO3
アンモニアから亜硝酸になるスピードより、亜硝酸が硝酸になるスピードの方がかなり早いため、亜硝酸はほとんど海水中にみられません。そのため、基本的にはアンモニアと硝酸の濃度を測ればよいと考えています。
硝化細菌ってなんなのって思う人もいるかもしれませんが、硝化細菌っていっぱいいすぎて正直よくわかってないです。アンモニアを硝酸に変えるバクテリアはいっぱいいます。単一では無いです。海水中には海水の淡水中には淡水の硝化細菌がいます。
ろ材にサンゴ砂を用いる理由
硝化細菌の働きにより、水槽内の硝酸濃度が増えるとpHが低下していきます。サンゴは塩基性の性質をもった炭酸カルシウムを主成分としているため、溶出することでpHの変化が抑えられます。(サンゴがあるのと無いのとでは全然pHが違います。)また、サンゴは多孔質な形状をしており、表面積を増やして単位体積あたりのろ過効率が高い、死サンゴは比較的安価に手に入るという点から様々な場所で活用されています。
ろ材別メリット・デメリット
pHの重要性
魚から排出されたアンモニアは海水中で乖離アンモニア(NH3)と非乖離アンモニア(NH4+)に分かれます。特に有害なのは乖離アンモニアで、乖離アンモニアの値には特に注意を払わなければなりません。
非乖離アンモニアと乖離アンモニアの割合は、海水の環境条件によって決まり、特にpHは大きな影響を与えます。pHが高いほど非乖離アンモニアの値が上がります。
アンモニアと硝酸の毒性
水槽で魚を飼う場合や、陸上養殖をする場合のそれぞれの対処法をお教えします。キットを使うことで簡易的な測定をすることができます。
アンモニアが発生している。
| 原因 | 対策 | |
| ① | ろ過能力が足りていない | アンモニアを処理するためのろ材の量が不足しています。 ろ材を増やすか、大きなろ過機をセットしましょう。 |
| ② | ろ材が立ち上がっていない | 通常アンモニアを処理できるようになるまで2−3ヶ月かかります。 魚の量を減らすか、できない場合は餌の量を減らしましょう。 |
| ③ | 餌のやりすぎ・魚が多い | 餌が残ってしまっている場合は取り除きましょう。 |
硝酸が多い
| ① | 水換えをしましょう。餌の量、魚の数を減らすと水換えの頻度を減らすことができます。 | |
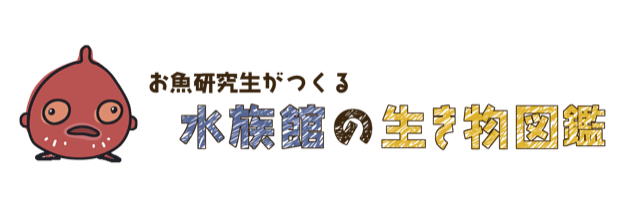



コメント